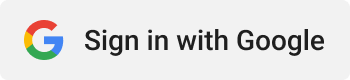ソムリエ試験の科目
ソムリエ資格試験は、一次試験から三次試験まであります。一次試験に合格した人だけが二次試験を受ける事ができます。また二次試験に合格した人だけが三次試験を受けることができます。
全てに合格しないと資格を取得できません。ただし、二次試験で不合格になった場合には、翌年から5年間は最大3回まで一次試験免除で再受験できます。三次試験で不合格になった場合には、翌年から5年間は最大3回まで一次と二次試験免除で再受験できます。
また、一度取得した資格は一生有効です。
一次試験(筆記試験)
マークシート方式の筆記試験で通常は4択です。試験時間は70分間で100〜130問の問題を解きます。2018年からCBT試験となり、60分120問となりました。
問題の80%程度はソムリエとワインエキスパート共通の問題です。残り20%が資格別に異なる問題です。2018年は100%同一の問題でした。
ワインの造り方や名前などが問われますが、かなり難しい問題もあり、ちょっとワインの事を知っているという程度では歯が立たないと思います。
合格ラインは公表されていませんが、独自の調査によると、毎年60〜65%くらいの正解が合格ラインのようです。問題が簡単な時は合格ラインは高めになり、逆に難しいときは低めになります。毎年ほぼ同じくらいの人数が合格するように調整されているようです。
なお、一次試験だけでの合格率は30%〜50%です。
二次試験(テイスティング試験)
ワイン、およびワイン以外のアルコール飲料(ブランデー、ウイスキーなど)をテイスティングし、外観、香り、味わいのコメントを行った上で、銘柄、産地、品種などを当てる必要があります。全てマークシート方式です。
出題される本数と試験時間が、資格によって異なります。
- ソムリエ資格
- 5本(ワイン3本、ワイン以外2本)、40分
- ワインエキスパート資格
- 5本(ワイン4本、ワイン以外1本)、50分
二次試験だけでの合格率は60%〜90%です。また、二次試験の難易度はソムリエとワインエキスパートでほぼ同じですが、年によってはワインエキスパートの方が少し難しくなります。
三次試験(論述試験とサービス実技)
三次試験は、ソムリエ資格で受験する人にだけ課されます。ワインエキスパート資格にはありません。
論述試験
論述試験は三次試験として審査されますが、二次試験と同じ日に行われます。例えば2018年には下記のような3問が出題されました。
- テイスティング2番のワインにおすすめする料理とその理由を説明してください。
- ジョージアワインについて説明してください。
- 日本のワイン輸入量No.1となったチリワインの今後の展望について説明してください。
時間は20分、いずれも200字程度書かなくてはいけないのでかなり忙しいです。
サービス実技
試験官がお客様役になります。そのお客様の前でワインの抜栓とデキャンタージュを行います。手順は決まっていて、基本的な動作をチェックされるだけです。高度な技を要求されているわけではありません。実際に日々お店で仕事をされている方なら、あまり難しくはありません。